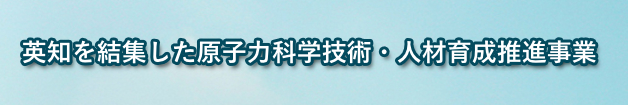英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業 > 研究分野の紹介 > 令和7年度 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業 課題解決型廃炉研究プログラム 選定課題
令和7年度 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業 課題解決型廃炉研究プログラム 選定課題
■課題解決型廃炉研究プログラム 合計6課題
■令和7年度選定課題:6課題
| No. | 提案課題名 | 研究代表者 [所属機関] |
参画機関 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臨界近接監視への適用を見据えたTlBr半導体検出器を用いたFPガスモニタの高感度化 | 渡辺 賢一 [九州大学] |
東北大学、日本原子力研究開発機構 | 福島第一原子力発電所の燃料デブリ取り出し作業を進める上で、再臨界に至らないよう臨界監視・管理を確実に行うことが重要である。現状では、核分裂で生成されるガス状核分裂生成物(FPガス)をモニタすることで再臨界に至っていないことを確認している。このFPガスモニタには高純度Ge半導体検出器が用いられている。本研究では、高実効原子番号・高密度で冷却の必要ないTlBr半導体検出器を用いることで、薄型の検出器を多層配置することが可能となり、システム全体としての検出効率を改善できる。これにより、従来より測定対象であったXe-135に加え、Kr-87,Kr-88についても測定対象となり、より早期の臨界検知およびPCV全体の未臨界度推定に繋がることが期待される。TlBr半導体検出器は、オールジャパン体制で開発を進める純国産技術で、メンテナンス性の観点からも、安全の根幹をなす機器の信頼性向上にもつながると期待される。 |
| 2 | 多粒径対応型荷電式スプレーとAI技術を統合した革新的エアロゾル制御技術の開発と実証 | 三輪 修一郎 [東京大学] |
日本原子力研究開発機構 | 福島第一原子力発電所(1F)における解体・除染作業への適用を見据えた、高効率なエアロゾル制御技術の開発を目的とする。1Fの燃料デブリ切断時には、サブミクロン領域の放射性エアロゾルが大量に発生することが想定されており、これらの粒子の施設外への拡散を防止するためには、高精度かつ信頼性の高いエアロゾル制御技術の確立が不可欠である。本提案では、エアロゾルの分散抑制に関する制御技術の高度化に加え、AI技術を組み合わせた微粒子計測・評価のための新たな解析モデルの開発を行う。具体的には、基礎実験で得られるデータをもとにAIモデルを構築し、さらに粒子法および数値流体力学解析を活用して、1F内部環境における放射性エアロゾルの挙動および熱流動現象の予測手法を整備する。これにより、実スケールでの解体・除染プロセスを模擬可能なシミュレーションツールの構築を目指す。さらに、PCV内部の流動環境下において、荷電させた水ミストおよびスプレーによってエアロゾルを効率的に捕集・制御するためのシステム設計と性能評価も実施する。最終年度には、これら一連の技術的要素を統合し、モックアップ試験を通じて構築したモデルおよびシステムの実用性と適用性を総合的に検証する。 |
| 3 | 超高線量率場における放射線環境情報取得を目指した無線線量計開発 | 黒澤 俊介 [東北大学] |
理化学研究所、産業技術総合研究所 | 福島第一原子力発電所の炉内の線量分布を見るために、これまで光ファイバーを用いた高線量率場モニタを開発してきたが、運用上そのファイバー利用が支障となる可能性がある。特にある程度ロボットなどが入れる環境下ではファイバーやケーブル類が運用の支障となる。そこで、ファイバーレスによる高線量率場をモニタする方法として、シンチレータ、太陽電池およびLED照明を用いた新しい線量計を開発する。この線量計自体は給電がなくても動作し、複数を設置して重心演算を実施することで撮像機能も獲得できる。当該システムの実現には、太陽電池とシンチレータの効率的な発電と、高線量率場環境下での太陽電池やLEDの放射線劣化を防ぐ点であり、このため新規太陽電池・シンチレータの開発を進め、放射線劣化しないような形状の当該線量計の開発を実施する。 |
| 4 | 1F廃棄物受入基準の設定に向けた安全評価シナリオの構築 | 渡辺 直子 [北海道大学] |
東海大学、東北大学、株式会社太平洋コンサルタント、電力中央研究所、日本原子力研究開発機構 | 福島第一原子力発電所の廃炉で発生する放射性廃棄物の処理・処分のための廃棄物受入基準(WAC)の策定に向け、現実的な安全評価シナリオを構築することを目的とする。固型化材として用いられるセメント系材料およびアルカリ活性材料(AAM)について、核種の移行抑制機能、浸出挙動に関する文献や海外動向の調査に基づき、特に易動性核種であるCやIを含めた核種について、セメント系材料、AAMを用いた移行挙動試験及び浸出挙動試験を実施する。この際、現実の放射性核種の濃度域でのHOT試験とCOLD試験を並行し、核種の移行挙動とそのメカニズムを明らかにする。さらに、模擬炭酸塩スラリーを用いて廃棄物擬似固化体を作製し、浸出試験を実施することで、固型化材単体で取得したデータの実廃棄体の評価への適応性を確認する。これらの知見をもとに、固型化材による収着や拡散などの核種の移行抑制機能が見込んだ、浸出速度や浸出量を組み込んだ核種移行予測モデルの構築を図る。 |
| 5 | α汚染可視化ハンドフットモニタ、可搬型ダストモニタ等の開発 | 北川 裕一 [北海道大学] |
産業技術総合研究所、日本原子力研究開発機構 | 1F廃炉事業の進展に伴い、作業者の被ばく管理に使用する可視化装置、高線量率作業現場で使用する可搬型α・βダストモニタ、さらに原子炉建屋内汚染箇所検査等に使用する高β線環境で使用可能なハンドヘルドα線検出器の開発を東京電力HD(株)、東双みらいテクノロジー(株)から求められている。 本事業ではR4年度英知事業「α汚染可視化ハンドフットクロスモニタの要素技術開発」の成果に基づき、(1)α汚染可視化ハンドフットモニタ、(2)高γ線環境対応可搬型α・βダストモニタ、(3)ハンドヘルド型ホスウィッチα線モニタを開発する。それに加え、(1)~(3)への応用を念頭に置いた(4)エアロゾルデポジション法によるZnS薄膜シンチレータとホスウィッチ検出器の最適化をすすめる。 (1)は新規開発した希土類錯体赤色発光シンチレータと高感度CCDカメラを組み合わせ、(2)は開発済のクロスモニタを応用し、総重量20kg以下を目指す。(3)は片手で持てる高β線環境対応のホスウィッチ型α線検出器であり、これらの開発により1F廃炉事業への貢献を目指す。 |
| 6 | 群知能を用いた多リンク型ロボットによる多視点環境情報計測及び試料採取技術に関する研究 | 趙 漠居 [東京大学] |
福島大学、日本原子力研究開発機構 | 1Fの廃炉現場においては、人的コストの低減、短時間での効率的な作業遂行、工期短縮、作業者の被ばく低減などの要求課題が多数存在する。これらを解決するにはロボットの利用が必須であるが、これまでは単体のロボットが各々の対象エリアを単独で調査していた。このため、放射能汚染の分布を含む環境情報や移動軌跡の情報がロボット同士で共有されず、人の手に依ってデータの結合や調査範囲の選定が成されていた。また、無線伝送が困難な高線量率の最奥部の情報取得には中継機が必要となる。一方で、高所の詳細な情報取得も到達困難なため、未だ実現できていない。さらに、故障により移動、データ伝送が困難になった場合はデータの取得はもとより、廃棄物の増加につながる。これは人的コストの低減を阻害することになり、さらには作業の長時間化につながる可能性がある。 そこで本研究は、デブリ取り出しの内部調査、モニタリングによる放射線源分布等の環境情報の把握に加え、試料採取を可能とする多リンク型のロボットに群知能を持たせることにより、自律的な連携操作技術の開発整備を行い、多視点からの放射線量率等の環境情報の把握等を行う。加えて、多リンク型構成を地上ロボットではなく、飛行ロボットに展開することで、高所での調査や採取等の作業が可能となる。このように、建屋内における3次元の環境情報を横方向と縦方向の両方から包括的に把握することでデブリ取り出し時の効率性向上が見込まれるため、廃炉作業を円滑に進めていく上で重要だと考えられる。また、群知能・多リンク型ロボット技術による複数の作業の連携操作は、試料採取を含めた現場へのアクション可能な要素技術であり、その利活用の範囲は広いと考える。 |
>> 戻る