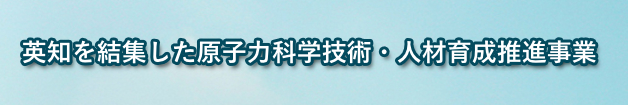英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業 > 研究分野の紹介 > 令和7年度 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業 国際協力型廃炉研究プログラム 選定課題
令和7年度 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業 国際協力型廃炉研究プログラム 選定課題
■国際協力型廃炉研究プログラム
| No. | 提案課題名 | 研究代表者 [所属機関] |
参画機関 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 難処理廃棄物への適用に向けたリン酸ガラス固化技術の開発 | 宇留賀 和義 [電力中央研究所] |
九州大学、Sheffield Hallam University | 福島第一原子力発電所(1F)で発生するALPS スラリーなどの水処理二次廃棄物は、線量が高く(137Cs, 90Sr: ~107Bq/cm3)今後も長期に亘り増加することや、HIC(*1)の放射線劣化による漏洩懸念などにより、高いリスクが評価されている。このため、国プロではガラス固化を含む様々な安定固化技術が検討されたが、現在はセメント固化とAAM(*2)固化について実用化に向けた研究が中心に行われている。一方、セメント固化やAAM固化では水素ガスが発生するため、処分場の受け入れが困難となる可能性がある。実際、英国や米国などの海外サイトでは住民を交えた長い議論の末、Cs/Sr廃棄物にはガラス固化が選ばれている事例があることから、国内でもガラス固化について水処理二次廃棄物への適用を見据えた検討を進めておくことが重要である。現状のガラス固化技術の適用には、高温で脱硝・溶融・流下を行う複雑で運転が難しい高価なガラス溶融炉が必要であり、加えて、水処理廃棄物の主要成分であるFe, Mg, Ti, S はホウケイ酸ガラスへの溶解度が小さいため固化体発生量が増加するという課題がある。そこで本研究では、これらの元素の溶解度が大きく、より低温で作製可能なリン酸ガラスによる廃棄物固化を検討するとともに、海外で検討されている外部加熱のIncan溶融法を直接通電法による内部加熱に改良することで、安価なガラス製造プロセスの開発を目指す。(*1)HIC=High Integrity Containe (*2)AAM=Alkali Activated Material(別名、ジオポリマー) |
| 2 | 燃料デブリ輸送のためのマルチフィジックスシミュレーションモデル | 酒井 幹夫 [東京大学] |
兵庫県立大学、産業技術総合研究所、日本原子力研究開発機構、 Department of Earth Science & Engineering, Imperial College London | 本研究は、廃止措置が進められている福島第一原子力発電所において、燃料デブリの安全輸送および再臨界を検討することを目的として、粉体・混相流の数値シミュレーション、臨界計算および縮約モデル(人工知能を使用)を融合した新たな計算手法を開発する。東京大学で独自開発した固気液三相流解析コードおよび縮約モデルとともに、JAEAで開発した連続エネルギーモンテカルロ法コードを用いて、燃料デブリの大規模回収に応用するための計算モデルを開発する。本研究の内容は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構により示された技術戦略プランにおける課題を解決するものであり、基盤研究として高い独創性を有することはもちろんのこと、我が国が長らく抱える燃料デブリの取り出しの重要課題の解決に貢献できるものである。原子力分野を研究する若手研究者の裾野を広げながら、原子炉廃止措置事業の信頼性と迅速性の向上に挑戦する。 |
>> 戻る